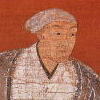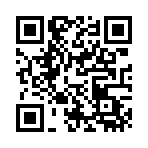2012年11月23日
黒田官兵衛⑪
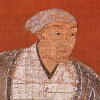
●幻の天下
1600年 (55歳)
関ヶ原の戦が起こると、九州で兵を集め、九州の統一からさらには天下取りへ向けた軍事行動を始めるが、予想外に早い決着により断念。
慶長3年(1598年)8月、豊臣秀吉が死去した。如水は同年12月に上洛し伏見屋敷に居住したという。この頃、如水が吉川広家宛てに「かようの時は仕合わせになり申し候。はやく乱申すまじく候。そのお心得にて然るべき候」と書いた書状が残されている。これは、如水が遠からず天下の覇権をめぐって最後の大乱が起きるであろうことを予想していたことを窺わせる。
慶長5年(1600年)、徳川家康らが会津の上杉景勝討伐のため東へ向かうと、7月17日(8月25日)石田三成らが家康の非を鳴らして挙兵し(西軍)、関ヶ原の戦いが起こった。黒田氏は当主・長政が家康の養女を正室として迎えていたことから秀吉の死去前後から家康に与し、長政は豊臣恩顧の大名を多く家康方に引き込み後藤基次ら黒田軍の主力を率いて家康に同行、関ヶ原本戦で武功を挙げた。
中津に帰国していた如水も、家康方(東軍)として行動した。 石田三成の挙兵の知らせを用意させていた早舟から受け取った如水は、中津城の金蔵を開いて領内の百姓などに支度金を与え、九州、中国、四国からも聞き及んで集まった9,000人ほどの速成軍を作り上げた。9月9日(10月15日)、再興を目指して西軍に与した大友義統(のちの宗麟)が毛利輝元の支援を受けて豊後に攻め込み、東軍の細川忠興の飛び地(本拠地は丹後国宮津)である杵築城を包囲攻撃した。城将・松井康之と有吉立行は如水に援軍を要請、同日、如水はこれに応じ、1万人と公称した兵力を率いて出陣した。 道中の諸城を攻略した後、9月13日(10月19日)、石垣原(現在の別府市)で大友義統軍と衝突した(石垣原の戦い)。母里友信が緒戦で大友軍の吉弘統幸に破れる等苦戦するも井上之房らの活躍もあって、黒田軍は大友軍に勝利した。
9月19日(10月25日)、富来城の攻略中に哨戒船が、東上中の城主である垣見一直からの密書を運んでいた飛脚船を捕え、西軍敗報に接する。その後、如水は藤堂高虎を通じて家康に領地切り取り次第を申し入れ、西軍に属した太田一吉の臼杵城(佐賀関の戦い)、毛利勝信の小倉城などの諸城を落としていった。 国東半島沖の豊後水道付近では、関ヶ原より引き上げてきた島津義弘の軍船と戦い(義弘が同行していた立花宗茂と別れた後のことである)、焼き沈めている。10月14日、如水は兵5000を柳川へ派兵し自身は西軍に参加した毛利秀包の居城である久留米城攻めへ向かう。鍋島直茂と鍋島勝茂が32000の兵を率いて久留米城攻めに参戦する。10月16日、柳川の支城である梅津城を落とす。その後、宇土城攻めを終えた加藤清正も参戦する。交渉の上、立花宗茂は降伏し如水軍に加わる。そして11月に入り如水は立花宗茂、鍋島直茂、加藤清正を加えた4万の軍勢で九州最後の敵勢力である島津討伐に向かったが11月12日に肥後の水俣まで進軍したとき、徳川家康と島津義久との和議成立による停戦命令を受け、軍を退き解散した。
黒田官兵衛⑫へ進む
黒田官兵衛⑩へ戻る
黒田官兵衛①から見る
Posted by 中津商工会議所 at 14:12
│軍師官兵衛